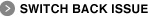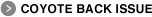ジョン・クラッセン・インタビュー「読者を信頼する職人」聞き手 柴田元幸

絵本「木に持ちあげられた家」の刊行を記念して、全二回にわたりジョン・クラッセンのインタビューを特別公開。
ジョン・クラッセン・インタビュー(第二回/全二回)
インタビュー=柴田元幸
「語らない」ことの手本たち
柴田 影響ということについて聞かせてください。絵本作家だけでなく、小説家や映画監督などで、影響を受けた人はいますか。
クラッセン むしろ絵本作家以外から影響を受けていますね。絵本でない方が、学ぶところがあったら応用もしやすいし。たとえばウィリアム・クリステンベリーという七〇~八〇年代に活動した写真家がいて、もっぱらアラバマの建物を撮っていました。同じ建物を、二十年くらいにわたって、何度も何度も撮る。凝った撮り方もせず、シンプルなカメラで。でも、その写真を通して、建物の劣化、成長、変化を見ていくと、すごく感情を刺激されるんです。
柴田 人も撮るんですか?
クラッセン 人は絶対撮りません。いつも建物だけ。でも彼が、それらの建物と心を通わせていることがわかるんです。だから、その建物が取り壊されてしまったのを見たりすると、とてもショッキングです。
小説家で一番好きなのはコーマック・マッカーシー(現代では稀な叙事詩的スケールで、しばしば暴力的な世界を描く、現代アメリカを代表する作家の一人)。彼の会話には、引用符がありません。誰が喋っているのか、きちんと考えながら読まないといけない。それに、「……と彼は哀しそうに言った」なんて書き方もしません。「……と彼は言った」だけ。その人がどう感じているか、文脈から考えるしかありません。その言葉少なさ、潔さが素晴らしい。表現にはすごく凝る人だけど、感情をいちいち説明したりはしません。彼もやっぱり、読者を信用していますね。
映画ではスタンリー・キューブリックがそう。遠くから撮って、感情を間近から映したりはしないから、何がどうなっているのか、観ている人間が決めないといけない。すごくミステリアスです。絵本でもそういうことをやりたいけど、子どもにそこまで根気があるかどうか(笑)。
柴田 そういうふうに、顔も描かない、感情も直接伝えたくない、という哲学でやっていると、絵本を出すのに苦労しないですか?
クラッセン 最初は苦労しましたね! でもあるとき、出版社が『木に持ちあげられた家』の物語を送ってきて、絵本にしないかと誘ってくれた。これなら僕も描けるかもしれないと思いました。家と木と空地の話なら僕にもできるかなと。で、だんだん物語を練り上げていくうちに、キャラクターも描かないといけない段階まで来た。でも人物同士が動き回っておたがい見つめあう、みたいな本はやりたくない。どうしたらいいかと思っていると、コーマック・マッカーシーの『ザ・ロード』が出て、これに大いに触発されました。すごくクリーンな本で、すごくグラフィックだった。シンプルでグラフィックな本では感情は伝わらないとか言うけど、そんなことはなかった。シンプルであるにもかかわらず感情が伝わってくるんじゃなくて、シンプルさ自体に感情がこもっているんです。ものすごく読者を信頼している。読みながら、本当に泣けてきます。シンプルさを通して感情を伝えることは可能なんだと教えられました。これが大きかった。それまでは……描くのが好きなのは椅子とかだけど、椅子じゃ絵本にならない(笑)。
柴田 絵を描くことは自然にできることじゃないとおっしゃるし、そもそもどうして絵本作家になったんですか(笑)。
クラッセン 描くのはいまだに苦労します。いまだに何も学んでない気がする(笑)。でも、好きではあったんです。すごく小さいときはそうじゃなかった。一年生のときに、リンゴを描きなさいとか言われても、何も描かなかった。でも、こういうおはなしを絵にしてごらん、と言われて初めて描く気になりました。いまだって展覧会のために絵を描く、とかいうのは全然惹かれない。皆さん、僕はリンゴをこんなに美しく描けるんですよ、とかね。物語と絵を組みあわせるのが楽しいんです。
ちょっとcreepy
柴田 カナダ人であるということで、違いはありますか? アメリカ人とは。
クラッセン あると思いたいです(笑)。アメリカに住むようになって八、九年経つけど、離れていればいるほど、自分はカナダ人なんだという思いが強くなってきます。『木に持ちあげられた家』にしても、物語を書いたテッド・クーザーは、たしかネブラスカに住んでいて、近所の家をモデルにしたんだけど、読んでいて僕は、オンタリオでよく見る、戦後すぐくらいに政府が建てた四角い家を思い浮かべました。まわりに林があって……やっぱりカナダで育ったことは影響しているでしょうね。カナダを愛しています。
柴田 日本の芸術はどうですか? 興味は?
クラッセン もちろん。まず版画。浮世絵とか、すごい技巧ですよね。山のてっぺんの白い雪とか、目を惹くけど、実はそこにインクは使ってない。それが効果的になるように、ものすごく丹念に、辛抱強く計画しているんですよね。
日本文化全体、アニメ、デザイン、イラスト、みんなすごく……クリーンです。宮崎駿の映画なども、顔は明快に描いてあって、感情もはっきりわかるんだけど、描き方が一種仮面のようというか、アメリカのアニメみたいに、怒った人はいかにも怒った表情、楽しそうな人はさも楽しそう、というふうにはやらない。やっぱりここでも、観る人を信頼していて、こっちの方がずっと効果的ですよね。
柴田 いろいろ伺っていると、あなたは読者を信頼する、アーティスト(芸術家)というよりアーティザン(職人)という気がします。ワークマンシップ(技量、熟練)を大切にしていて。
クラッセン うん、「アーティスト」という看板には頼りたくない。たとえばアートディレクターや編集者と意見が合わなくても、「アーティストは俺だ」みたいなことは言いたくない。「これが僕のビジョンだ。これを信じてもらわないと」とか。きちんと、論理的に説明しないといけない。だから作品を渡すときも、自分が作ったものを「アート」と呼ぶ気はしません。「品(ピース)ができました」とか「イラスト完成しました」とか言う。僕がやっていることはエンターテインメントです。届くべき読者がいて、解決すべき問題がある。それはアートとは違います。 柴田 自分の絵本のときは、絵と言葉と、どっちが先に?
クラッセン 言葉。でもほかの人とやるときは、そうとは限りません。
柴田 え、絵を先に描くということ?
クラッセン たとえば、『くらやみ こわいよ』は、子どもが懐中電灯を持って、階段の下を照らしている、そういう絵がまず一枚あったんです。でも、そこからどういうストーリーにしたらいいかわからない、と編集者に言ったら、じゃあレモニー・スニケットに書いてもらおう、と。
編集部 『木に持ちあげられた家』のカバーはどうやって決めたんですか?
クラッセン たしか三つか四つ案があって、はじめ一番気に入っていたのは、屋根が高い木々に囲まれてほとんど埋もれたようになっている絵でした。そういうのってめったに見ない光景ですよね。でもそれは、結末で起きることだから、表紙で見せてしまうのはまずい。だけどよく考えてみると、「木に持ちあげられた家」というタイトルで、結末をすでに伝えているんですよね。本全体、何のトリックもなく、詩的な文章で、何のてらいもなく、タイトルで宣言したとおりのところへ持っていく。だから絵の方は、結末を見せるのはやめて、本のなかのどこにも属さない瞬間を描きました。ちょっとミステリアスに、ちょっとcreepy(不気味)に。出版社もそれは理解してくれて、この文章なら水彩画のキレイキレイな本に仕立てることもできるけど、ちょっとcreepyで行こう、と言ってくれた。
柴田 ちょっとcreepy、ってあなたの大半の本に当てはまりそうですね。
クラッセン ははは。creepyな本は子どものころから好きだったな。
柴田 僕はエドワード・ゴーリーの翻訳者なんですが、彼なども……
クラッセン ゴーリー! 大好きです。彼が描いた、ジョン・バキャンの『三十九階段』という小説の表紙はすごいですよね。大きな岩が、ぽっかり宙に浮かんでいて……。あるいは、ドアから脚が二本、突き出ているだけで、人が殺されていることを伝える。手を抜いてるんじゃなくて、読者の想像力に任せてるんです。
子どもが相手だと、彼らがまだ受け容れる態勢ができていないものを見せたくはない。脚が二本、突き出ているだけなら、そこから子どもが何を読みとろうと、それはすでに子どもの頭のなかにあるものです。しかもそれが子どもを死ぬほど怯えさせる。すごいですよ。エドワード・ゴーリーは僕の英雄の一人です。
柴田 最後に、いま取りかかってらっしゃる本。Sam and Dave Dig a Hole(サムとデイヴ、穴を掘る)というタイトルだそうですが、完成しましたか?
クラッセン うん、ホテルから昨晩ファイルを送りました。
柴田 おめでとうございます! 読めるのを楽しみにしています。
(二〇一四年三月八日、Rainy Day Cafeにて)
写真=森本菜穂子
▶︎WEB CONTENTS